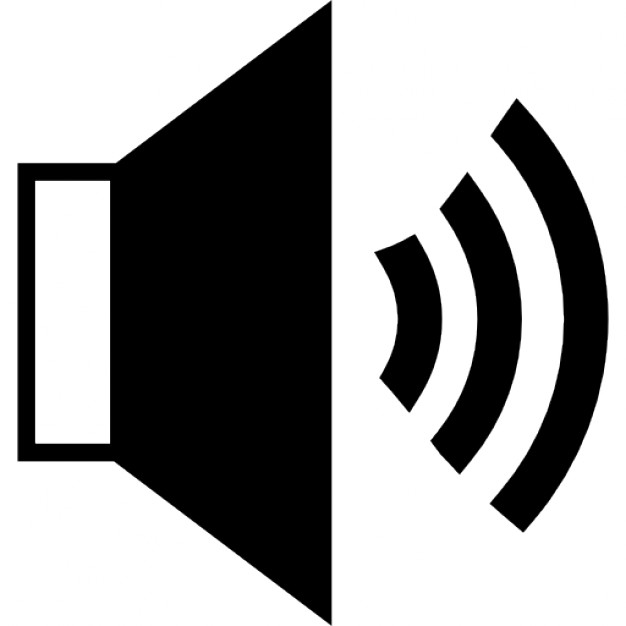会社で自分の席に内線電話があるけど、かかってきても電話を取るのが怖い・・・。
そんなことはないでしょうか。
会社にかかってくる電話を取ることは、とても大事な業務のひとつです。
というわけで、電話を取るためのまとめをつくりました。
そもそも、なぜ電話を取るのが怖いのか

なぜ電話に出るのが怖いのか。
考えられる要因としては次のようなものがあります。
電話に出るのが怖くなる要因
- 固定電話を使った経験がない!
- 知らない相手からの電話に出るのは億劫!
- 電話機の操作がよくわからない!
- 電話を取ったときの対応のしかたがわからない!
- 誰に取り次ぐのかよくわからない!
- 電話が鳴ってから応答するまでのコール数がわからない!
携帯電話やスマホの普及がすすんだ現在では、固定電話を置かない家も増えてきています。
とくに入社したての新入社員の方たちは、携帯やスマホのあつかいには慣れていても、固定電話は触ったことすら無いという人も、中にはいらっしゃることでしょう。
会社にかかってくる電話は、必ずしも自分が知っている相手からかかってくるわけではありません。
逆によく知らない相手からかかってくることのほうが多いことでしょう。
- 知らない相手からの電話に出るのが億劫で電話を取る機会が減る
- 電話を取る機会が減るとますます電話に出るのが億劫になる
このような悪循環にハマっているかたも多いのではないでしょうか。
家庭用の電話機と違い会社で使っているビジネスフォンの電話機はボタンが多くついています。
外線ボタン、保留ボタン、転送ボタン、短縮ボタン、フックボタンなどビジネスフォンの機種や電話機によって様々なボタンがついています。
それらのボタンを駆使して電話を使わなければならいないのですが、
- 応答の仕方 がわからない
- 保留の仕方 がわからない
- 取次の仕方 がわからない
- 発信の仕方 がわからない
このように電話機の操作がわからないままだと、電話を取りたくなくなりますよね。
- 電話を取ったときに、どのような対応をすればいいのかわからない。
社外からかけてきた人と、社内からかけてきた人では当然対応も変わります。
対応のしかたがわからないままでは、電話を取りたいとは思わないですよね。
- 電話を取ったのはいいものの、誰に取り次ぐのかよくわからない。
- 取次先の人の内線番号がわからない、あるいは取次操作自体よくわからない。
多くの人がこの「取り次ぎ」が壁になっているのではないでしょうか。
電話が鳴り始めてすぐに応答する人もいれば、1~2コールあえて取らずに応答する人もいるかと思います。
会社や部署によって、電話に応答する推奨のタイミングが異なることも少なくありません。
応答するまでのコール数がわからないので、とりあえず様子見、つまり電話に出ない、というようなことにはなっていませんか?
電話を取れないことを克服するためには?

電話を取ることへの抵抗をなくすために、次のような準備をしましょう。
- 電話の操作を確実に覚える
- 電話を取った時の文言を用意しておく
- スムーズに取り次げるように、内線番号表を目に見えるところに用意する
- 電話が鳴ってから応答するまでのコール数を周囲に確認しておく
対策1. 電話の操作を確実に覚える

電話の操作がわからないから、電話を取りたくない、というのであれば電話の操作を確実にマスターしてしまいましょう。
決して難しいものではありません。
外線着信に応答する
外線着信に応答するときは大体次のような操作になります。
- 受話器を上げるだけで応答する
- 光っている外線ボタンを押して応答する
- 応答ボタンを押して応答する
ビジネスフォンの設定によっては、外線着信時に受話器を上げるだけで応答できるようになっていることがあります。
外線着信すると電話機の上部にたくさんついている外線ボタンが光るので、そのボタンを押して外線着信に応答します。
外線着信したときに、応答ボタンを押して応答します。
同時に外線ボタンが光っているケースが多いですが、光っているボタンを気にせずにとにかく応答ボタンを押して応答します。
通話を保留する
通話を保留するときは次のような操作になります。
- 保留ボタンを押して保留する
- パーク保留ボタンを押して保留する
- 転送ボタンを押して保留する
- 自己保留ボタンを押して保留する
通話中に保留ボタンを押して通話を保留します。
外線通話中だったときは外線ボタンに通話が保留されるか、空いているパーク保留ボタンに自動的に保留されます。
保留ボタンそのものに保留されることもあります。
パーク保留ボタンは複数個あることが多いので、ランプが消灯しているパーク保留ボタンを押すと、そのパーク保留ボタンに通話が保留されます。
転送ボタンを押しての保留は、ほとんどの場合、別の内線をダイヤルして通話を取り次ぎたいときに使用します。
自己保留ボタンを押しての保留は別の内線に通話を取り次がずに、しばらく待ってもらうようなときに使用します。
通話を取り次ぐ
通話を保留したあとは、取り次ぐ操作につながることが多いです。
- 口頭で近くの人に取り次ぐ
- 内線をダイヤルして取り次ぐ
- 放送して取り次ぐ
保留操作をしたあとは、外線ボタンかパーク保留ボタンに保留されるケースが多いので、近くの人の電話機も同じように保留中のランプが点滅しています。
近くの人に保留の旨を口頭で伝えて、保留中のランプを押してもらったら取り次ぎ完了です。
保留操作後に取り次ぎ先の内線番号をダイヤルして内線を呼び出しします。
内線が応答したら取り次ぐ旨を伝えて受話器を下ろすか転送ボタンやフラッシュボタンを押すことで取り次ぎが完了します。
取り次ぎ先相手がどこにいるのかわからない場合は、電話機から放送の操作を行い相手に伝えます。
放送の操作は放送特番をダイヤルするか、放送ボタンを押して行います。
相手には保留しているボタンの番号などを伝えれば、近くの電話機から保留応答してくれることでしょう。
保留中のランプが点滅から消灯、あるいは点灯に変われば相手が保留に応答したことになるので取り次ぎ完了です。
近くの内線の代わりに応答する
近くの内線に内線着信している場合に、自分の内線電話機から代わりに応答することができます。
その場合、代理応答の特番をダイヤルするか、代理応答ボタン、あるいはピックアップボタンを押して代わりに応答します。
電話の操作について詳しくはこちら

対策2. 電話を取ったときの文言を用意しておく

電話を取ったときになんて言っていいのかわからない場合は、あらかじめ電話に出たときの文言を目に見えるところに用意しておきましょう。
- 自分「はい、○○株式会社の○○が承ります」
- 相手「いつもお世話になっております。XX商事のXXと申します。△△様はいらっしゃいますか?」
- 自分「いつもお世話になっております。お繋ぎしますので少々お待ち下さい」
- 自分「はい、○○株式会社の○○です」
- 相手「お疲れ様です。XX部のXXですが、△△さんはいますか?」
- 自分「お疲れ様です。少々おまちください」
対策3. スムーズに取り次げるように内線番号表を目に見えるところに用意する

通話を取り次ぎする際に、取り次ぎ先の内線番号がわからなければ、取り次ぎに時間がかかってしまいます。
取り次ぎ先がすぐにわかるように内線番号表を見やすいところにあらかじめ用意しておきましょう。
取り次ぎ頻度の高い内線があるようならワンタッチボタンに登録しておくと、取り次ぎ操作がスムーズに行えます。
また取り次ぎ先の通話状態がランプ表示されるので取り次ぎ可能かどうかひと目でわかってとても便利です。
対策4. 電話が鳴ってから応答するまでのコール数を周囲に確認しておく

電話が鳴ってから応答するまでのコール数に部署内などで決まりがあるかもしれないので、周囲にあらかじめ確認をとっておきましょう。
とくに決まりがないようでしたら、1~2コール以内、おそくとも3コール以内に電話に出れば問題ないかと思われます。
最後に
電話を取るのが怖いのは、たいていの場合、よくわからないことへの苦手意識からくるものです。
- 電話の操作
- 応答したときの文言
- 取り次ぎ先の把握
これらを把握しておけば、電話に出ることなんて造作もないことです。
何回か回数を重ねれば、電話にでることなんて何とも思わなくなることでしょう。
最後までご覧いただきましてありがとうございます。